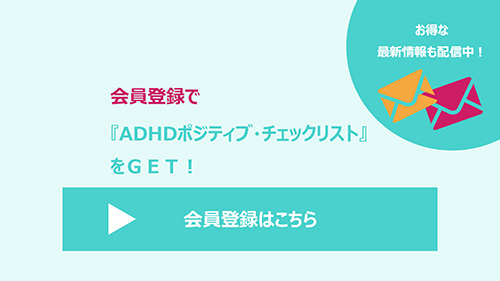こんにちは!リーベル・りなこです。
暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしですか?
先日、シネスイッチ銀座にて上映中の映画『歓びのトスカーナ』を観ました。
舞台は陽光がまぶしく輝くイタリアのトスカーナ。
心に傷を負った2人の女性ベアトリーチェとドナテッラが自由を求めて診療施設を脱走し、繰り広げる珍道中。次々に沸き起こるトラブルの中、徐々に二人の絆は深まっていきます。
そんな中、ドナテッラは自分にはある目的があることを思い出し、ベアトリーチェは彼女の願いを何とか叶えてあげたいと思うのでした…。
とにかく、二人の女優さんの演技が素晴らしい!
自由奔放で破天荒なベアトリーチェ、孤独と悲哀に満ちたドナテッラから終始目が離せませんでした。
そして、こちらの映画、背景には「精神保健システムの在り方」という大きなテーマがあります。
イタリアには、精神病院というものが存在しません。国内の様々な改革を経て、2000年以降には完全廃止されました。ちなみに、日本は精神病院数が他国に比べ爆発的に多い国です。
だからといって、イタリアは患者さんをほったらかしにしている訳ではありません。
各地域には、多様な分野の専門家チームからなる保健センターが配置されていて、最先端のサポートを受けることができるのです。映画では、人々の様々な喜怒哀楽が描かれていて、イタリア社会の寛容さを伺うことが出来ました。
そして、映画の中で特に印象的だったシーンがあります。
ベアトリーチェがある夫婦から「あなたは心理士か何かですか?」とドナテッラとの関係を尋ねられるシーン。
ベアトリーチェはこう答えます。「心理士以上の関係です」と。
サポートは人と人とのコミュニケートであり、それは医療以外でも可能です。その人の気持ちを知りたい・理解したいという心の寄り添いがあることで、お互いの希望をもたらすことが出来ます。
そして、そこにはお互いの勇気も必要です。
今回の映画を観て、ADHD/発達特性サポートもイタリアの精神保健システムに学ぶことがあると感じました。
例えば、
- サポートを必要とする人自身の主体性(生きる力)を重視したケア(横のつながり)
- 国、地域の各分野の専門家・サポーター(医療、福祉、教育、就業、法律など)とのオープンな連携システムの構築化、など。
困りごとは生活の中で発生します。だからこそ、提供する人もそれを必要とする人も、孤立することなく社会の中で対応することが大切なのではないでしょうか。
人は、ほんのちょっとの思考の転換で、幸せにも不幸せにもなれるものです。
必要と思っていたことが不必要だったり、不必要と思っていたことが必要だったり、「もう終わりだ!」と思っていたことが始まりだったり…。
それを行うのは、他の誰でもなく、自分自身。
「サポートとは何か?」「幸せとは何か?」…
そんなことを改めて見つめることができる、とても素敵な作品でした!
ADHDリソースセンターでは各種ご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。